ロードバイクのトレーニングを科学的に管理したいと考えたとき、多くのサイクリストが「TSS」という言葉に出会います。しかし、このTSSとは一体何なのでしょうか。この指標は、感覚だけに頼らない客観的なトレーニング管理を可能にするための重要な鍵となります。この記事では、ロードバイクのTSSとは何かという基本を徹底解説し、具体的な活用法まで詳しくご紹介します。TSSの計算方法を正しく理解することはもちろん、計算の鍵となるIF(強度係数)とは何か、回復の目安となるTSSの数値についても分かりやすく説明します。また、TSSは高ければ良いわけではない理由や、自身の感覚、つまり主観的疲労度と組み合わせるのがコツである点も、安全で効果的なトレーニングを行う上で欠かせない視点です。さらに、ガーミンでのTSS自動計算機能やStravaを使ったTSS管理方法、一週間のTSS目標設定の考え方、TSS500は超高強度のサインであることなど、実践的な知識も網羅します。年齢や目的別のTSS活用術を知ることで、最終的にロードバイクのTSSとは指標の正しい理解がいかに重要かをお分かりいただけるはずです。
- TSSの基本的な意味と計算の仕組み
- TSSの数値を基にした回復期間の目安
- ガーミンやStravaを使った具体的なTSS管理方法
- オーバートレーニングを防ぐためのTSS活用術
ロードバイクのtssとは?基本を徹底解説
- TSSの計算方法を正しく理解する
- 計算の鍵となるIF(強度係数)とは
- 回復の目安となるTSSの数値
- TSSは高ければ良いわけではない理由
- 主観的疲労度と組み合わせるのがコツ
TSSの計算方法を正しく理解する

ロードバイクの世界:イメージ
TSS(トレーニング・ストレス・スコア)とは、著名な運動生理学者であるアンドリュー・コーガン博士によって提唱された、1回のトレーニングで身体にどれだけの生理学的負荷(ストレス)がかかったかを数値化する指標です。この指標の優れた点は、トレーニングの「時間(量)」と「強度(質)」という2つの異なる要素を、科学的根拠に基づいて一つの数値に統合していることです。これにより、短時間で息が上がるような高強度のインターバル練習も、何時間もかけて走る長距離のエンデュランスライドも、同じ土俵で負荷を客観的に比較・評価できます。この数値を継続的に記録・分析することで、自身の成長度合いを客観的に把握し、感覚だけに頼らない計画的なコンディション管理が可能になります。
TSSを算出する上での絶対的な基準となるのが、FTP(機能的作業閾値パワー)で1時間走り続けた場合の負荷を「100 TSS」とする点です。FTPとは、サイクリストが1時間持続できる最大の平均パワーを指し、有酸素運動能力の重要な指標とされています。つまり、TSSは各サイクリスト個人のFTPを基準(100%)として、その日のトレーニングがどれくらいの負荷だったのかを相対的に示してくれます。これにより、FTPが異なるライダー同士でも、同じTSSであれば同程度の生理学的ストレスを受けたと解釈できるのです。
TSSの計算式
TSSは以下の計算式によって求められます。
TSS = (トレーニング時間[秒] × NP® × IF®) / (FTP × 3600) × 100
この計算式は一見すると複雑に感じられるかもしれません。しかし、現在市販されている多くのサイクルコンピューターやトレーニングアプリが自動で計算してくれるため、サイクリスト自身がこの式を暗記する必要はほとんどありません。重要なのは、TSSが単純な運動時間だけでなく、NP®(標準化パワー)やIF®(強度係数)といった「強度」の要素を極めて重視しているという概念を理解することです。
※NP®, IF®, and TSS® are registered trademarks of Peaksware, LLC.
例えば、信号でのストップ&ゴーや急な下り坂でパワーがゼロになる瞬間が頻繁にあるライドでも、NP®は変動するパワー出力を生理学的な負荷に基づいて補正し、一定ペースで走り続けた場合に近い数値を算出します。このため、単純な平均パワーで計算するよりも、より体感に近いトレーニング負荷をTSSとして正確に数値化できるのです。
計算の鍵となるIF(強度係数)とは
とは-1024x558.jpg)
ロードバイクの世界:イメージ
TSSの計算において、トレーニングの「質」を決定づける非常に重要な役割を果たすのがIF®(インテンシティ・ファクター)、日本語では「強度係数」です。これは、そのトレーニング全体の強度が、自身のFTPに対してどれくらいの割合だったかを示す、0から1.0(あるいはそれ以上)の範囲で表される指標です。IF®は、トレーニング全体のNP®(標準化パワー)を自身のFTPで割ることで算出されます。
IF®(強度係数)の計算式
IF® = NP® (標準化パワー) / FTP (機能的作業閾値パワー)
例えば、FTPが250Wのサイクリストが、あるトレーニングでNP®が225Wだった場合、そのライドのIF®は「225 ÷ 250 = 0.90」となります。これは、FTPの90%に相当する強度でトレーニングを行ったことを意味します。
IF®の数値を見れば、その日のトレーニングがどれだけハードだったかを一目で、そして客観的に把握できます。以下にIF®の数値が示す一般的な運動強度の目安を示します。
| IF®の数値 | 運動強度の目安 | 該当するトレーニング例 |
|---|---|---|
| 0.75未満 | 低い強度 | アクティブリカバリー(積極的休養) |
| 0.75 – 0.85 | 中程度の強度 | エンデュランス走、長時間のLSD |
| 0.85 – 0.95 | 中〜高強度 | テンポ走、SST(スイートスポット) |
| 0.95 – 1.05 | 高い強度 | FTPインターバル、タイムトライアル(1時間程度) |
| 1.05 – 1.15 | 非常に高い強度 | タイムトライアル(20分程度)、クリテリウム |
| 1.15以上 | 極めて高い強度 | 短時間のインターバル、トラック競技 |
TSSの計算式からも分かるように、TSSはIF®の「2乗」に比例して増加します。これは、運動強度が高くなればなるほど、身体への生理学的ストレスは非線形的に、つまり爆発的に増大するという事実を反映しています。つまり、IF®がわずかに0.1上がるだけでも、TSSの蓄積量は大きく跳ね上がるのです。このため、効果的なトレーニング計画を立てる際には、走行時間だけでなくIF®を常に意識することが非常に重要になります。
回復の目安となるTSSの数値
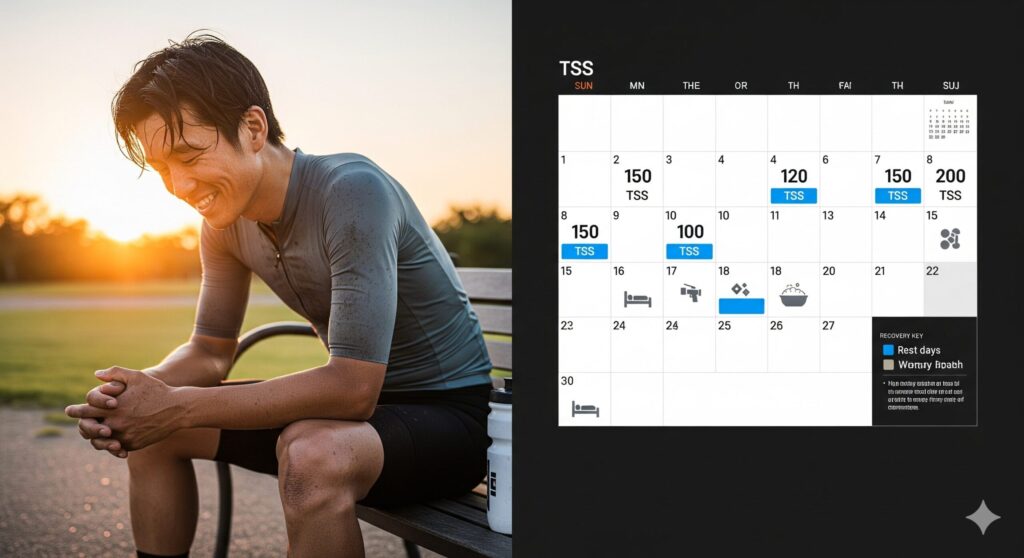
ロードバイクの世界:イメージ
TSSを日々のトレーニングで記録する最大のメリットの一つは、トレーニング後の回復に必要な時間や休息の質を客観的な数値に基づいて見積もれる点です。トレーニングで蓄積したTSSの数値によって、身体がどの程度の疲労状態にあるのかを客観的に判断し、次のトレーニングまでの適切な休息期間を計画できます。これにより、感覚だけに頼った結果生じがちなオーバートレーニングや、逆にトレーニング不足といった事態を防ぐことができます。一般的に、TSSの数値と回復の目安は以下のように分類されています。
これはあくまで一般的な目安です。年齢、その日の体調、栄養摂取の状況、睡眠の質、さらには仕事などの精神的ストレスによっても、回復力は大きく個人差が出ます。ご自身の感覚とデータ、両方を大切にして判断するのが賢明ですよ。
| TSSの数値 | 疲労のレベル | 回復の目安 |
|---|---|---|
| 150以下 | 低い | 翌日にはほぼ回復し、次のトレーニングに影響は少ない |
| 150 – 300 | 中程度 | 翌日に軽い疲労が残るが、翌々日にはほぼ回復する |
| 300 – 450 | 高い | 回復に2日以上を要し、翌々日も明らかな疲労が残る可能性がある |
| 450以上 | 非常に高い | 完全に回復するまで数日間を要する。計画的な完全休養が必須 |
具体的な例で考えてみましょう。例えば、平日の夜に1時間程度の集中したインターバルトレーニングを行い、TSSが80だったとします。この場合、適切な栄養補給と睡眠をとれば、翌日には問題なく回復し、次の日のトレーニングにも臨めるでしょう。しかし、週末に仲間と150kmのロングライドに出かけてTSSが350に達した場合は、状況が異なります。この場合、翌日は完全な休養に充てるか、筋肉をほぐす目的のごく軽い回復走(TSS20-30程度)にとどめるのが賢明です。もしここで無理に高強度の練習をすれば、回復が追いつかず、週後半のトレーニングの質を落としたり、体調を崩したりする原因になりかねません。このようにTSSを基準にすることで、「なんとなく疲れているから休む」という曖昧な判断ではなく、データに基づいた戦略的なコンディション管理が可能になるのです。
TSSは高ければ良いわけではない理由
TSSという便利な指標を知ると、「とにかく高いTSSを稼げば強くなれる」という思考に陥りがちですが、それは大きな間違いです。TSSはあくまでトレーニングの「負荷量」を測るツールであり、その数値の高さがトレーニングの「質」の高さを直接示すわけではありません。むしろ、TSSの絶対値だけを盲目的に追求することには、深刻なリスクが伴います。
高TSSだけを追求することの危険性
- オーバートレーニングのリスク:人間の身体が成長するためには「トレーニング(負荷)」と「回復」の両方が不可欠です。自身の回復能力を超えた高いTSSを継続的に積み重ねると、疲労が抜けきらずにパフォーマンスが慢性的に低下する「オーバートレーニング症候群」に陥る危険性が高まります。
- トレーニングの質の低下(ジャンク・マイル):例えば、FTP(持続力)の向上を目的とするなら、FTP付近の強度で集中的に行うSST(Sweet Spot Training)が質の高いトレーニングとして知られています。しかし、ただTSSの数値を稼ぐためだけに、目的意識なく長時間ゆっくり走る(いわゆるジャンク・マイル)だけでは、目的とする能力の向上には効率的に繋がりません。同じTSS200でも、その中身が重要です。
- 怪我や故障のリスク増大:身体的・精神的な疲労が蓄積した状態で無理にトレーニングを続けると、ペダリングフォームが崩れたり、注意力が散漫になったりします。これは、膝や腰の痛みを引き起こす原因となるだけでなく、路上での判断ミスによる落車や事故など、深刻な怪我に繋がる可能性を著しく高めます。
最も重要なのは、「何のためにトレーニングをするのか(目的)」と「自身の回復力を考慮した負荷(バランス)」です。持久力を高めたいベース期間には、長時間のライドで高いTSSを目指すことが有効な戦略となります。一方で、レースに向けて瞬発力やスピードを高めたい時期には、合計のTSSは中程度に抑えつつも、強度の高いインターバルトレーニングで神経系や無酸素エネルギー供給系を刺激することが重要になります。TSSはあくまでトレーニングを管理するための一つの指標であり、数字の奴隷になるのではなく、賢く活用することが継続的な成長への最短ルートとなります。
主観的疲労度と組み合わせるのがコツ

ロードバイクの世界:イメージ
TSSはパワーデータに基づいてトレーニング負荷を客観的に評価するための非常に優れた指標ですが、決して万能ではありません。なぜなら、TSSが生理学的ストレスを算出する一方で、私たちのコンディションに影響を与える他の多くの要因を直接は反映できないからです。具体的には、睡眠不足、仕事や家庭の精神的ストレス、夏の暑さや冬の寒さといった環境要因による消耗、さらには高強度トレーニングによる筋肉の微細な損傷などは、TSSの数値には直接現れません。
多くのサイクリストが経験することですが、例えば真夏の炎天下で厳しいヒルクライムに挑戦した場合、パワーメーターが示すTSSの数値自体は150程度でも、身体は脱水や体温の異常上昇によって疲労困憊し、翌日も全く動けない、ということがあります。このような客観的な数値と、自身の体感との間に生じる「ズレ」を補うために極めて重要になるのが、RPE(Rating of Perceived Exertion)、つまり「主観的運動強度」や「主観的疲労度」を併用することです。
TSSと主観的疲労度(RPE)を併用する具体的な方法
トレーニングログ(アプリや手帳など)にTSSの数値を記録する際、その日の体調や「トレーニングがどれくらいキツかったか」を、例えば1から10の10段階評価(ボルグスケールなどが有名)で一緒にメモしておくことをお勧めします。これを継続することで、自身のコンディションをより多角的かつ正確に把握できます。
- Case 1:TSSは高いが、RPEは低い(思ったより楽だった)
→ 身体がトレーニングに適応し、フィットネスが向上している良いサインかもしれません。 - Case 2:TSSは低いのに、RPEは高い(数値以上にキツかった)
→ 睡眠不足や他のストレスが原因で、見えない疲労が溜まっている可能性があります。次のトレーニング強度を計画的に落とす、あるいは勇気をもって休養するという判断ができます。
TSSという数値データは、私たちの判断を助けてくれる客観的な道しるべです。しかし、最終的にペダルを漕ぎ、トレーニングの負荷を受け止めるのは自分自身の身体に他なりません。データに頼りすぎるのではなく、自身の身体が発する声に真摯に耳を傾けること。これこそが、オーバートレーニングを未然に防ぎ、長期的に、そして安全に成長していくための最も重要なコツと言えるでしょう。
ロードバイクのtssとは?具体的な活用法
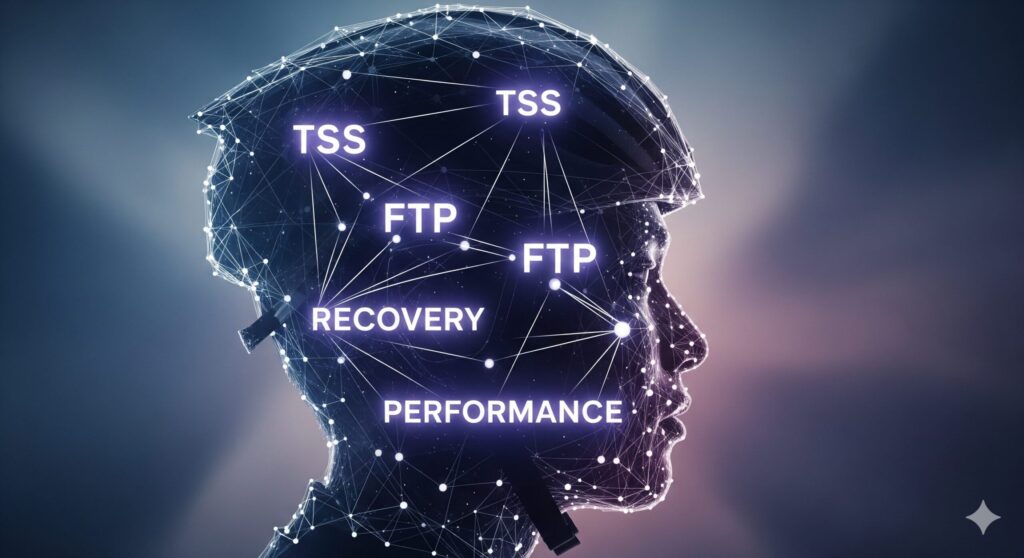
ロードバイクの世界:イメージ
- ガーミンでのTSS自動計算機能
- Stravaを使ったTSS管理方法
- 一週間のTSS目標設定の考え方
- TSS500は超高強度のサイン
- 年齢や目的別のTSS活用術
- ロードバイクのtssとは指標の正しい理解が重要
ガーミンでのTSS自動計算機能

ロードバイクの世界:イメージ
現在、世界のサイクリストから絶大な支持を得ているGarmin(ガーミン)のサイクルコンピューターには、TSSをはじめとする各種パワーデータを自動で計算・記録する機能が標準で搭載されています。この先進的な機能を活用することで、サイクリストは複雑な計算から解放され、日々のトレーニング負荷の管理を極めて簡単に行うことができます。
TSS計測に必須となる機材
ガーミンのデバイスでTSSを正確に計測するためには、基本的に以下の2つの機材が必要不可欠です。
- パワーメーター対応のサイクルコンピューター:Edge 540, 840, 1040といった現行のEdgeシリーズをはじめ、多くのモデルが対応しています。
- パワーメーター:ペダル型(Garmin Rallyなど)、クランク型(Shimano, SRAMなど)、ハブ型など、自身の自転車に取り付け、ペダルを漕ぐ力をワット(W)単位で計測できるセンサーです。
これら2つの機材をANT+やBluetoothといった無線通信でペアリングし、事前に自身の最新のFTP値をガーミンデバイスに設定しておくだけで準備は完了です。あとは通常通りライドを開始すれば、ライド終了後に自動でその日のTSS、NP®、IF®といった重要なデータが算出され、スマートフォンアプリのGarmin Connect上で詳細に確認できます。さらに、走行中にリアルタイムでTSSの数値をデータ項目として表示させることも可能です。これにより、「今日の練習はTSSを120まで積む」といった具体的な目標を立てながら走ることができ、トレーニングの質を一層高めることができます。
FTP値はトレーニングによって常に変動します。少なくとも4〜6週間に一度はFTPテストを行い、最新の数値をデバイスに設定し直すことが非常に重要です。FTPが変わればTSSの算出基準そのものが変わるため、正確な負荷管理のためにもこの更新作業を忘れないようにしましょう。
Garmin Connectでは、過去のトレーニングデータも無期限に蓄積されるため、週ごとや月ごと、年ごとのTSSの推移をグラフで視覚的に確認することもできます。これにより、トレーニング量や強度が計画通りに増えているか、あるいは意図的に休息(リカバリー)が取れているかを一目で把握でき、より計画的で効果的なトレーニングの実践に大きく貢献します。
Stravaを使ったTSS管理方法

ロードバイクの世界:イメージ
サイクリスト向けのソーシャル・ネットワーキング・サービスとして絶大な人気を誇るStrava(ストラバ)も、TSSを活用したトレーニング管理において非常に強力なツールです。特に、有料のサブスクリプション機能に含まれる「フィットネス&フレッシュネス」チャートは、日々のTSSを基にした長期的かつ戦略的なコンディション管理を可能にします。
Stravaでは、Garminなどのデバイスから同期されたライドデータをもとに、TSS(Strava上では「相対的エフォート」や、パワーメーター使用時は「トレーニング負荷」として表示)を自動で計算してくれます。そして、この日々のTSSデータを継続的に積み重ねることで、パフォーマンス管理において重要な以下の3つの指標を、分かりやすいグラフで時系列に示してくれます。
Stravaのフィットネス&フレッシュネスで示される3つの主要指標
- フィットネス (CTL – Chronic Training Load):過去42日間のTSSの加重平均値。長期的なトレーニング負荷の蓄積を反映し、いわゆる「地脚」や「体力」がどれだけ向上しているかを示します。
- 疲労 (ATL – Acute Training Load):過去7日間のTSSの加重平均値。直近のトレーニングによる短期的な「疲れ」の度合いを示します。
- フォーム (TSB – Training Stress Balance):現在の「フィットネス (CTL)」から「疲労 (ATL)」を差し引いた値(TSB = CTL – ATL)。レース当日に向けたコンディションの仕上がり具合を示し、プラスの値が大きいほど身体がフレッシュ、マイナスの値が大きいほど疲労が蓄積している状態を意味します。
このグラフを定期的にチェックすることで、「フィットネス(CTL)の数値を右肩上がりに徐々に高めつつ、目標とするレースやイベントの1〜2週間前からはトレーニング量を調整して疲労(ATL)をしっかり抜き、フォーム(TSB)をプラスに持っていく」といった、プロ選手も実践するような戦略的なコンディション調整(ピーキング)が可能になります。例えば、フィットネスの数値が何か月も停滞している場合はトレーニング計画の根本的な見直しを検討したり、疲労の数値が急激に上昇し続けている場合は、意図的に休息日を設けたりする客観的な判断ができます。TSSを単発のライドの負荷(点)として見るだけでなく、長期的なコンディションの推移(線)で捉えるために、Stravaの分析機能は非常に有効なツールと言えるでしょう。
一週間のTSS目標設定の考え方

ロードバイクの世界:イメージ
日々のトレーニングでTSSを記録することに慣れてきたら、次のステップとして「一週間という単位で、どれくらいのTSSを目標にするか」という中期的な計画を立てることが重要になります。闇雲に「先週より多く」といった曖昧な目標を掲げても、継続できなければ意味がありませんし、怪我のリスクを高めるだけです。自身の現在のフィットネスレベルや、トレーニングに割ける時間、そして生活スタイル全体を考慮して、現実的かつ効果的な目標を設定することが求められます。
CTLを基準とした負荷の漸進
一週間のTSS目標を設定する上で、非常に有効な考え方が、前述のCTL(フィットネス)を基準にする方法です。CTLはあなたの身体が現在慣れている長期的なトレーニング負荷の平均値を示しています。フィットネスを安全に向上させるための基本原則は「漸進性過負荷」、つまり少しずつ負荷を上げていくことです。そのため、一週間の合計TSSが現在のCTLの7倍を大きく、かつ継続的に超えている場合、負荷が高すぎて回復が追いつかない可能性があります。逆に、それよりも常に低い状態が続いている場合は、体力を維持、あるいは向上させるには負荷が足りないかもしれません。まずは、一週間の合計TSSが「CTL × 7」を基準とし、そこから週に5〜10%程度の増加を目指すのが、安全かつ効果的な負荷の上げ方とされています。
一般的なホビーサイクリストの週間TSS目安
もちろん個人差は非常に大きいですが、仕事や家庭生活と両立しながらトレーニングを行う一般的なホビーサイクリストの場合、一週間の合計TSSは400~700程度の範囲でも、計画的に継続すれば十分に体力を向上させられると言われています。世界のトッププロ選手は週に1000 TSSを超えることもありますが、彼らはトレーニングと回復に専念できる環境にあります。限られた時間の中でパフォーマンス向上を目指す私たちは、無理のない範囲で質の高いトレーニングを継続することが最も大切です。
また、もう一つ重要なのが、毎週同じTSSを目指すのではなく、「3週間かけて徐々に負荷を上げていき、4週目は積極的な回復週として負荷を意図的に大きく落とす」といった周期(ピリオダイゼーション)を取り入れることです。この回復週を設けることで、身体が蓄積した疲労をリセットし、トレーニングによって得られた刺激に適応する(超回復)時間が確保されます。これにより、オーバートレーニングを防ぎながら、効率的にフィットネスレベルを一段階上へと引き上げていくことが可能になるのです。
TSS500は超高強度のサイン

ロードバイクの世界:イメージ
日々の計画的なトレーニングとは別に、グランフォンドのような特別なイベントや、個人的な限界に挑戦する過酷なライドに臨む機会もあるでしょう。その際、サイクルコンピューターに表示されるTSSの数値が、普段のトレーニングとはかけ離れた異次元の値を示すことがあります。特に、1回のライドでTSSが500を超えるような場合は、それはあなたの身体に「超高強度」かつ「極めて大きな」生理学的負荷がかかったことを示す明確なサインです。
TSS500という数値が、具体的にどれほどの負荷なのかをイメージするために、いくつかの例を挙げてみましょう。
- 走行距離250kmを超えるような長時間のロングライドイベント(ブルベなど)
- 獲得標高が4000mを超えるような、過酷な山岳サイクリング
- 市民レースの中でも特に距離が長く、強度の高いロードレース
- 複数日にわたるアマチュアのステージレースにおける、クイーンステージ(最難関ステージ)
このような活動では、サドル上の走行時間が8時間、9時間と長時間に及ぶことも珍しくありません。その結果として、TSSが500、コンディションやコースによっては600や700といった数値に達することもあります。これは、本記事で示した回復の目安で言えば「非常に高い」レベルをはるかに超える、例外的な負荷です。このようなライドを経験したことがある方なら深く共感できると思いますが、ライド後数日間はまともに階段を上ることも困難なほどの筋肉痛や、全身の倦怠感に襲われることが少なくありません。
TSS500を超えた後に絶対に行うべきこと
TSS500を超えるような極限的なライドの後は、最低でも2〜3日、理想を言えばそれ以上の積極的な回復期間(アクティブリカバリーや完全休養)を設けることが絶対的に必要です。この期間に無理してトレーニングを再開すると、筋肉や結合組織の修復が追いつかないだけでなく、免疫力が著しく低下して感染症にかかりやすくなったり、ホルモンバランスが崩れて慢性的な疲労状態に陥ったりするリスクが非常に高まります。良質な炭水化物とタンパク質を中心とした食事、そして十分な長さと質の睡眠にも、普段以上に気を配り、身体を内側から回復させることを最優先に考えてください。
TSS500という数値は、大きな挑戦を乗り越えた達成感の証であると同時に、あなたの身体が発している最大級の危険信号でもあります。このような高負荷のライドは、事前のトレーニングで十分なTSS耐性をつけた上で計画的に行い、その後のリカバリープランまでをトレーニング計画の一部としてセットで考えることが、長く安全に自転車というスポーツを楽しむための、サイクリストとしての重要な責任です。
年齢や目的別のTSS活用術

ロードバイクの世界:イメージ
TSSは、プロ選手からサイクリングを始めたばかりの初心者まで、全てのサイクリストにとって有用な客観的指標ですが、その最適な活用方法は個々の年齢、フィットネスレベル、そしてトレーニングの目的によって大きく変わってきます。自分に合ったTSSの管理方法を見つけることが、貴重なトレーニング時間を無駄にせず、効率的なレベルアップを達成するための鍵となります。
40代以降のホビーレーサー:量より質を重視したスマートな活用
40代以降になると、若い頃に比べて回復力が緩やかに低下してくるのが一般的です。また、仕事や家庭における責任も増え、トレーニングに割ける絶対的な時間や体力も限られてきます。このような状況で、20代の頃と同じように高TSSをただ追い求めるのは、非現実的であるばかりか、怪我や燃え尽き症候群のリスクを高めるだけです。重要なのは「量より質」への転換です。短い時間で効率よくFTP(持続走能力)を刺激するSST(スイートスポットトレーニング)や、短時間で心肺機能に強い刺激を入れるVO2maxインターバルなどを中心にメニューを組み、週間の合計TSSは400~600程度でも、計画的に継続すれば十分にパフォーマンスは向上します。無理な計画で睡眠時間を削ることはせず、回復を最優先にしたスマートなトレーニング計画を立てましょう。
ヒルクライムが目標のサイクリスト:目的に特化したTSSの蓄積
ヒルクライムレースで結果を出すためには、体重比パワー(PWR)の最大化、特に高いFTPの維持が不可欠です。そのため、トレーニングの目的は「FTPの向上」に明確に絞られます。長時間のLSD(低強度長時間走)でTSSを稼ぐことも基礎的な有酸素能力の維持には役立ちますが、それ以上に、FTP向上に直接的に繋がるSSTやLT(乳酸性作業閾値)インターバルといった、質の高い高強度のトレーニングを重視すべきです。これらのトレーニングは、走行時間が短いため1回あたりのTSSの数値自体はそこまで高くならないかもしれませんが、目的が明確な質の高いトレーニングを積み重ねることが、ヒルクライムのパフォーマンス向上に最も効率的に繋がります。
ロングライド・ブルベが目標のサイクリスト:高TSS耐性の計画的養成
200km、300km、さらには600kmといった長距離を、制限時間内に、そして安全に走り切るためには、高いFTPだけでなく、長時間にわたってパワーを出し続ける能力、つまり「高TSS耐性」を養う必要があります。この場合は、トレーニング計画の中に、意図的に長時間のライドを組み込み、1回のライドでTSSが300を超えるような経験を計画的に積んでおくことが非常に重要になります。もちろん、毎週そのような高負荷をかけることはできませんから、「平日は疲労を抜きつつ短時間で質を確保し、週末にドカンと時間をかけて量をこなす」といった、メリハリのあるトレーニング計画が求められます。また、実際のイベントに近い状況をシミュレーションし、補給食の摂取方法やペース配分を練習しておくことも重要です。
このように、ご自身の目標を明確にすることで、TSSという客観的な指標をどのように活用すべきか、その戦略が見えてきます。自分に合った使い方を見つけ、トレーニングを最適化していきましょう。
ロードバイクのtssとは指標の正しい理解が重要
- TSSはトレーニングの量と強度を科学的に数値化した負荷の指標
- FTPで1時間走行した際の身体的ストレスが100TSSの絶対的な基準となる
- 計算には時間だけでなくIF(強度係数)が2乗で大きく影響する
- IFは個人のFTPに対する相対的な運動強度を示す重要な数値
- 運動強度が少し上がるだけでTSSは非線形的に急激に上昇する
- TSSの数値はトレーニング後の回復に必要な期間の客観的な目安として活用できる
- TSS150以下は翌日に回復可能だが300を超えると数日の回復期間が必要となる
- TSSの数値が高いことが必ずしも良いトレーニングを意味するわけではない
- オーバートレーニングや怪我のリスクを避けるため回復とのバランスが最も重要
- TSSでは睡眠不足や精神的ストレスなど数値化できない疲労は測れない
- 自身の体感である主観的疲労度(RPE)と組み合わせて多角的に判断することが大切
- ガーミンなどのサイクルコンピューターはパワーメーターと連携してTSSを自動計算してくれる
- Stravaの有料機能を活用すればTSSを基に長期的なコンディション(CTLやTSB)を管理できる
- 一週間のTSS目標は自身の現在のフィットネスレベル(CTL)を参考に漸進的に設定する
- 高負荷をかける週と意図的に負荷を落とす回復週を組み合わせる周期的な計画が効果的








